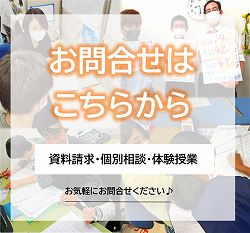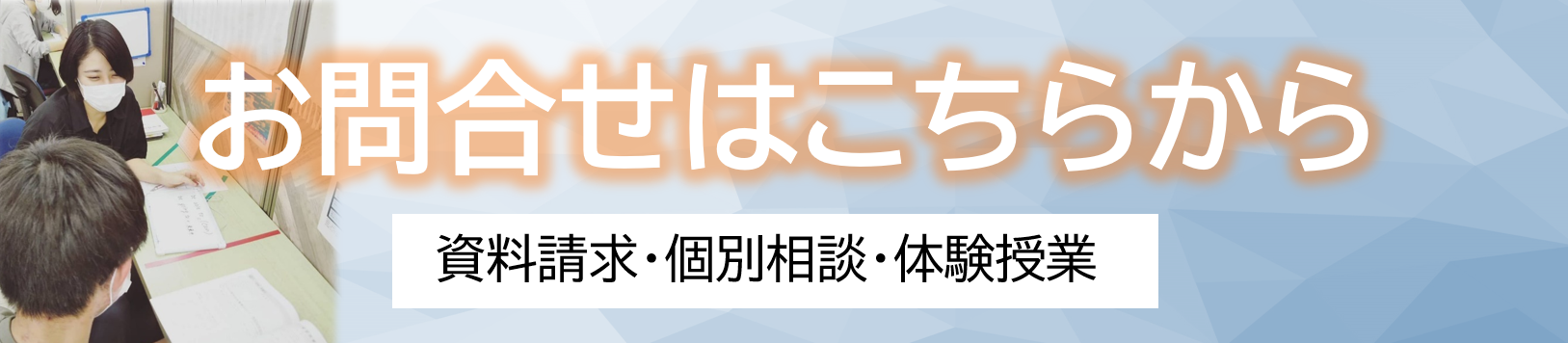失敗しない塾の選び方~これだけで決めてはいけない塾選び~
「塾の選び方」第2回目です。
今回のテーマは「間違った塾選びの方法」です。
「正しい(後悔のない)塾選び」をするためには「間違った塾選び」をしないことが大切です。
ぜひ参考にしてください!
これだけで決めてしまうとキケン…!な塾選び2選
◆友達が通っている
◆月謝が安い
一つずつ見ていきましょう。
友達が通っている

「友達が通っているから」は塾を決めるうえで多くの方が重視するポイントの一つです。
確かに友達と一緒に通うことで良きライバルとなり相乗効果を生み出すケースは非常に多いです。
夏期講習明けのある日、中3生の女の子が言いました。
「私ひとりだったら絶対こんなにやれなかった。〇〇が一緒に頑張ってくれたから私も頑張れた」
このようなケースも実際少なくありません。
しかし一方で気をつけなければならないのは「友達には合っていた塾が自分にも合っているとは限らない」という点です。
個別塾が合っていた子は個別塾を、集団塾が合っていた子は集団塾を勧める場合が多いため、「本当は個別に行きたかったのに集団塾を勧められて断れなかった」ということにならないよう注意が必要です。
もう1つ、「目的の履き違い」という側面も忘れてはなりません。
そもそも塾は勉強をする場所・勉強を通して成長する場所であるにも関わらず、友達と一緒の場合その目的がいつの間にか
「友達と会うこと」「おしゃべりすること」になってしまうことがあります。
本来の目的を見失わないことが大切です。
月謝が安い

数ある塾の中には「えっ、これでどうやって運営しているの!?」とつい思ってしまう料金設定のチラシやHPを目にすることがあります。
低料金は魅力の一つではありますが、次の2点を心に留めておいてください。
①月謝以外の諸経費が高いケース
たとえチラシやHP上で記載されている月謝は安くても、実際に面談で話を聞いてみると入会金・施設管理費・教材費・テスト代・その他雑費等の「諸経費」が高額な場合が少なくありません。
授業料だけでなく、それ以外の諸経費も含めた「総額」をチェックすることが大切です。
②人件費・人材育成費を削減しているケース
塾を運営する中で最も大きな割合を占める1つが「人件費」です。人件費を削減することで確かに月謝を抑えることは可能です。
しかしそのしわ寄せは教室長に必ずやってきます。
スタッフ不足に陥り、授業のほとんどを教室長が担当するといった場合も少なくありません。そうなると予習や授業準備に手が回らず、結果的に授業の質が下がってしまうというリスクを含んでいます。
教室長が担当している授業量を事前に確認してみると良いでしょう。
まとめ
今回はキケンな塾選びというテーマに沿ってお伝えしました。
ではこれらを踏まえて今後どんな行動をとれば良いのか。
何と言っても実際に教室に足を運び、そこの教室長と直接会って話をしてみることが大切です。
どんな人が出てくるのか、知っている友達がいるのか、料金の総額はいくらか、実績はどうなのか、スタッフの様子や雰囲気は子どもに合っているか…
これらを正確に把握するためには、やはり実際に足を運んでご自分の目で確かめないことには分かりません。
塾選びは子どもたちの生活に大きな影響を与えます。
後悔の無い塾を見つけられるよう、第一印象や見た目の看板力だけではなくそこで働いている「人」や「雰囲気」といったアナログな部分も検討材料にしてもらいたいと思います。
次回は「アップステーションが選ばれる理由」です。乞うご期待!